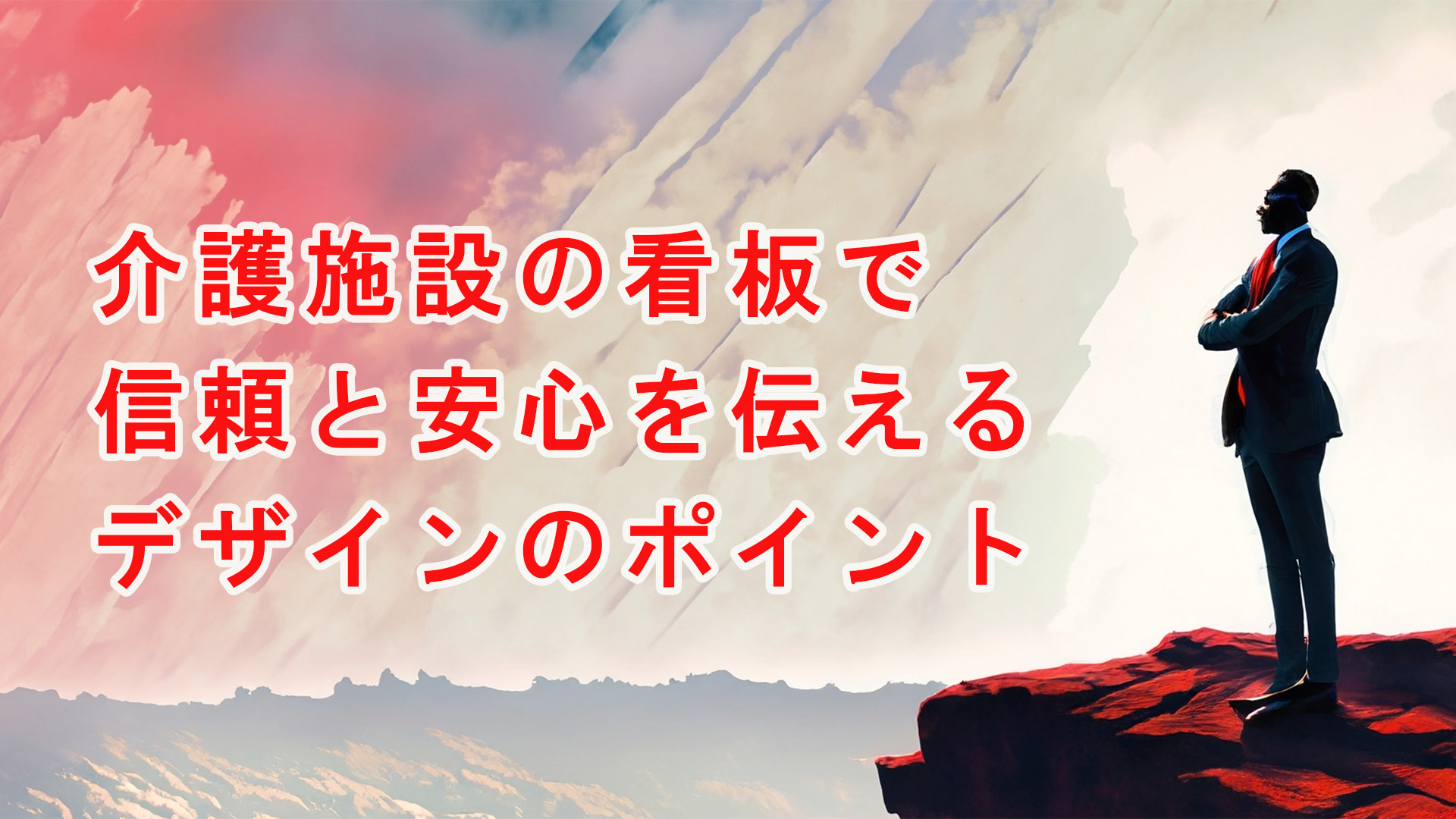
少子高齢化が進行する中、社会では介護施設の役割が益々増しています。需要の高まりに応じて施設の数も増え、競争は激しくなっています。そんな中で、多くの人から求められる施設となるためには、「信頼」と「安心」を看板を通じて利用者に伝えることが大切です。この記事では介護施設を対象に、看板デザインのポイントを解説します。
▽介護施設の看板に求められる役割とは?
介護施設に入所する際は、本人もその家族も不安になるものです。看板はそういった方々に向けて、施設の理念や想いを伝える重要なツールです。看板を制作する前に、どのような役割を持たせるべきか確認しておきましょう。以下では、介護施設の看板が果たすべき4つの主な役割を紹介します。
安心感と信頼感を与える表現
介護施設の看板は、利用者が最初に目にする「施設への入り口」です。不安を解消するため、他業種の看板と異なり、派手さよりも「安心」を優先したデザインが求められます。
・色彩の選択
できるだけ派手な色は避け、落ち着いた色合いを使用しましょう。不安を解消するには温もりを感じさせる色彩が適しています。
・フォントと形状
冷たい印象を与えるおしゃれな書体よりも、視認性の高い太めの書体や、角を丸めた優しい形状が好まれます。
・シンボルとなるグラフィック
手をつなぐイラストや介護スタッフの笑顔など、ケアの温かさを連想させる要素をイラストや写真などのグラフィックで取り入れましょう。
施設の特徴と差別化ポイントの明確化
競合施設が多い介護業界では、看板を通じて自施設の長所や強みを端的に伝えることが集客の鍵となります。
・特化サービスの強調
認知症ケアやマンツーマンのリハビリプログラムなど、他施設にはない独自サービスを強調しましょう。
・地域密着のアピール
地域の文化や特産品をデザインに取り入れ、地元愛や地域住民とのつながりをアピールすると好感度が上がります。
・実績や利用者の声
「○○人が利用」や「専門資格保有スタッフ在籍」などの実績、利用者の感想を記載することは、サービスの内容理解に繋がり、信頼性を高めます。
アクセシビリティとユニバーサルデザインの実践 PR
介護施設の利用者には視覚や身体機能に制約のある方も多いため、看板も「誰にでもわかりやすいデザイン」に仕上げることが求められます。
・文字サイズとコントラスト
視力の下がった高齢者でも読みやすい大きな文字と、白地に黒い文字といった背景との明瞭な色差を意識しましょう。
・多言語対応
地域に外国籍の利用者がいる場合、英語や中国語で追記することも検討しましょう。デイサービスの看板では、送迎バスの到着時間や利用可能時間を言語によらずアイコンで表示する事例もあり、利便性向上に貢献しています。
地域コミュニティとの信頼構築
介護施設は地域に根ざした存在であるため、看板は「地域社会との架け橋」としての役割も担います。
・地域の課題を反映
高齢者の孤立防止や子育て支援など、地域が抱える問題への施設としての取り組みをメッセージに盛り込みます。
・イベント情報の発信
高齢者の孤立防止には地域イベントが役立ちます。認知症講座や健康チェック会などのイベントを施設の看板で告知し、地域住民の参加を促しましょう。
▽優しさと信頼感を演出するデザインの工夫
潜在的な施設利用者の心に響く看板は、「優しさ」と「信頼感」を表現するものです。介護施設の看板デザインでは、商業施設のような目立つことを重視するのではなく、「心に寄り添う」ことが大切です。前章でも色使いなど少し触れましたが、ここではデザインの工夫について介護施設ならではのポイントを深掘りします。
色彩心理学を活かした「癒しの色」
介護施設の看板で重要な要素の一つは、高齢者や家族の不安を和らげる色彩選びです。医療機関のような無機質な白や青ではなく、できるだけ「温もり」と「安心」を両立させる配色が鍵となります。
〇ベースカラー
・ベージュやアイボリー
自然素材を連想させ、緊張感を緩和する効果があるのでお勧めです。
・薄い緑(ミントグリーン)
ストレス軽減効果が期待できるリラックスカラーで、看板に適しています。
〇アクセントカラー
・サーモンピンク
北欧の介護施設で使用例が多いとされ、孤独感を軽減し、幸福感を喚起する効果が期待できます。
・深みのある紺色
伝統的な日本らしい落ち着きのある色合いで、お年寄りに好まれます。専門性と清潔感を同時に表現できるのがメリットです。
「触れたくなる質感」で生まれる親近感
他業種では軽視されがちな触覚を意識した質感は、介護施設の信頼感を左右する要素になり得ます。ふと触れた時の「手触り」やそれを連想させるイメージが無意識の安心感を醸成します。
〇自然素材の活用
・杉板の凹凸加工
木目の温かみと滑り止め効果が合わさり、高齢者に優しいデザインと言えます。
・石材の活用
重厚感と「永続性」を表現することができます。日本らしさも生まれます。
〇特殊加工テクニック
・UVコートによるマット仕上げ
反射光を抑え、目の疲れを軽減できます。
・立体文字の角丸加工
鋭利なエッジを排除し、丸みのある優しい印象を強調しましょう。
注意点
車いす利用者が触れる可能性を考慮し、高さ60〜120cmの範囲に鋭利な装飾を避けます。
「読む」ではなく「感じる」 非言語コミュニケーションのデザイン
認知機能が低下した方にも伝わるよう、文字情報に依存しないイラストなどを多用した「直感的なメッセージ」を組み込みます。グラフィックで工夫できるポイントを挙げました。
〇シンボルイラストの法則
・手のデフォルメ
介護スタッフの手を少し大きめに描くことで「支える気持ち」を表現できます。
・コミュニティの連帯をモチーフ
結束やコミュニティのつながりを連想させる、「輪になって笑う高齢者とスタッフ」のようなデザインは安心感を与えます。
〇光の演出:
・間接照明付き看板
夜間は看板を柔らかい光で照らし出し、「24時間見守る姿勢」をアピールしましょう。
・影を使った立体感
文字に薄い影を加え、視力の弱い方にも認識しやすくなります。
「動き」と「余白」が生む心理的な安心感
情報が頭に入ってこない掲示物は不安感を与えます。高齢者の視覚特性に配慮し、情報過多にならない「見やすく心が落ち着くデザイン」を意識しましょう。
〇視線誘導の黄金ルール:
・Z字型レイアウト
左上→右上→左下→右下の自然な流れで情報を配置しましょう。自然と頭に入ってきやすいレイアウトです。
・余白比率を30%以上に
パニック障害のある方にも圧迫感を与えない、ゆとりのあるスペース設計です。
〇動的要素の抑制
・点滅LEDの不使用
癲癇発作を引き起こしてしまうリスクを回避しつつ、常時微光で存在感を維持しましょう。
・ゆるやかなグラデーション
急激な色変化ではなく、夕焼けのような自然な移行が理想です。
▽施設のイメージを高める看板の設置場所
看板の設置場所はデザインと同じくらい重要な要素です。潜在的な施設利用者に「私たちのことを考えていない設置場所だな」と思われてしまうと、施設のサービスの信頼性を損ないます。ここでは、施設のイメージ向上に効果的な看板の設置場所とその理由を解説します。
施設の入口周辺
入口は施設の「顔」となる場所であり、訪れた家族や見学者が最初に目にする場所です。この入り口に清潔で明るいデザインの看板を設置することで、「安心できる施設」というメッセージを伝えられます。看板の高さは歩行者目線(約1.5m)に合わせ、イラストや優しい色使いで親しみやすさを表現しましょう。
周辺道路や駅からの導線
施設の存在を地域に知ってもらうためには、主要道路や駅からのアクセス経路など、潜在的な利用者が多く存在する地点に看板を設置し、認知度を高める必要があります。車で通行する人向けに、視認性の高い大型看板を交差点付近に配置すると良いでしょう。
施設内の共有スペース
施設内の廊下やロビーなど、家族が滞留するスペースに、施設の理念やスタッフの思いを伝える看板を設置しておくと、信頼関係の形成に役立ちます。スタッフの紹介や資格取得状況を掲載し、専門性をアピールしましょう。利用者の作品を展示したり活動写真を掲載したりするのも、活気のある日常を伝えられて親しみやすくなります。
協力店舗や公共施設に設置する「連携看板」
地域とのつながりを強めることで、地域コミュニティにおける施設の社会的信頼度が向上します。「あの施設なら安心できるね」と話題に上がるように、協力店舗や公民館などに看板を設置し、地域貢献をアピールしましょう。
▽まとめ
看板は「施設の想いを反映する媒体」です。利用者は施設のサービスに向き合う姿勢を、看板のデザインや設置場所から感じ取ります。優しく安心できる施設であることを看板というメディアを通じて伝え、不安を解消しましょう。制作する際のポイントは多岐に渡るので、専門家にも相談しつつ、最適な看板を目指しましょう。






